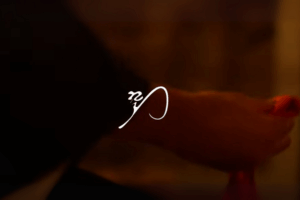「お茶会に招待されたけれど、何を持っていけばいいの?」「着物じゃないとダメ?」そんな疑問をお持ちの方へ。この記事では、お茶会に必要な持ち物を必須アイテムと便利グッズに分けて詳しく解説します。流派による違いや、初心者の方でも安心して参加できる服装マナー、当日の流れまで、お茶会デビューに必要な情報を網羅的にご紹介。正式な茶事から気軽な大寄せの茶会まで、この記事を読めばお茶会への不安が自信に変わります。
お茶会の種類を知ろう

お茶会と一口に言っても、実は様々な形式があります。持ち物や服装を準備する前に、まずはどのようなお茶会に招かれているのかを確認しましょう。お茶会は大きく分けて「茶事」と「大寄せの茶会」の二つに分類されます。
正式なお茶会「茶事」とは
茶事は、茶道における最も正式なお茶会の形式です。懐石料理から始まり、濃茶、薄茶と続く一連の流れを、約4時間かけて丁寧に楽しみます。招待される人数は5名程度の少人数で、主に親しい方や茶道を学んでいる方が招かれることが多いでしょう。
初心者の方がいきなり茶事に招かれることは稀ですが、最近では初心者向けの茶事体験教室や、寺院が主催する茶事イベントなども開催されています。茶事に招かれた際は、持ち物や服装について、事前に主催者に確認することをおすすめします。
気軽に楽しめる「大寄せの茶会」
大寄せの茶会は、文字通り多くの参加者を招いて開催される、より身近なお茶会です。薄茶席のみの気軽なものから、立礼式(椅子席)のお茶会まで、初心者でも参加しやすい形式が多く開催されています。
都内では、「東京大茶会」や「銀茶会」といった大規模なイベントが季節の風物詩として定着しており、カジュアルな雰囲気の中で本格的なお茶を楽しむことができます。初めてお茶会に参加される方は、まずこうした大寄せの茶会から体験されることをおすすめします。
【必須】お茶会に必ず持っていくべきもの

お茶会に参加する際、必ず用意しておきたい基本の持ち物をご紹介します。これらは茶道の作法において欠かせないアイテムです。
懐紙(かいし)

懐紙は、お菓子をいただく際に使用する和紙で、お茶会では必須のアイテムです。男性用と女性用で大きさが異なり、女性用は約14.5cm×17.5cm、男性用はそれより一回り大きいサイズになっています。
お茶会には新しい懐紙を1帖(20〜30枚綴り)用意しましょう。特に正式な茶事の場合は、白無地の懐紙が基本です。大寄せの茶会では、季節の柄が入った懐紙を使用することもありますが、初めての参加の際は白無地を選ぶと安心です。
懐紙は、お菓子をいただく時だけでなく、お茶碗の飲み口を拭く時や、ちょっとした汚れを拭き取る時など、様々な場面で活躍します。使った懐紙は折りたたんで持ち帰るのがマナーです。汚れた面を内側にして小さく折りたたみ、帰宅後に処分しましょう。
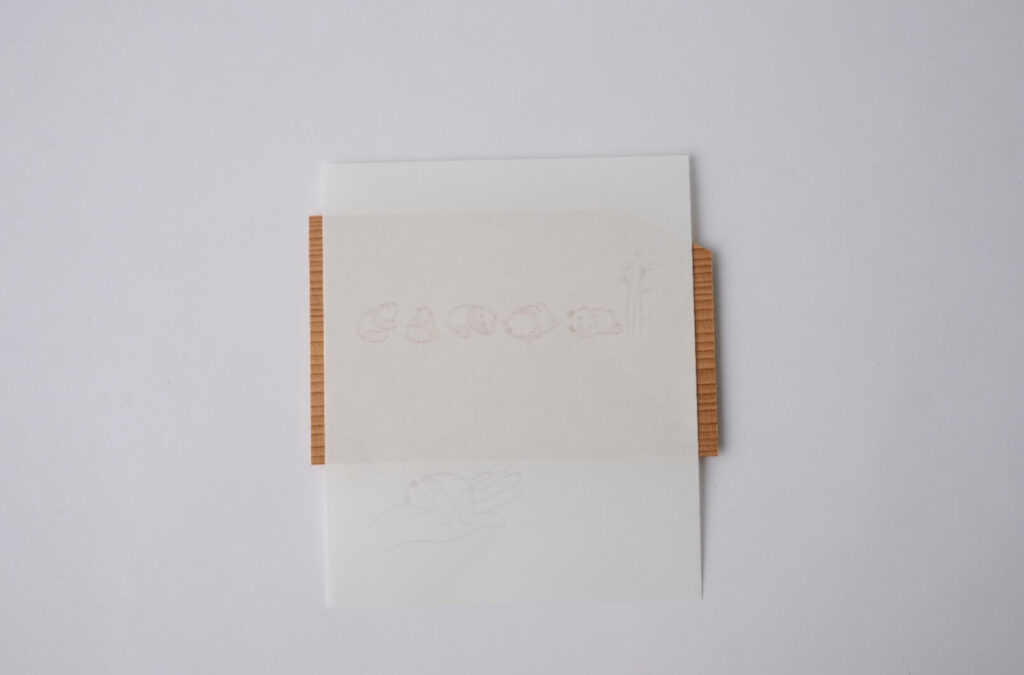
こちらはパンダのデザインをあしらった懐紙です。お茶会や茶道のお稽古などで使用する懐紙には香りやカラフルなものはNGです。無地であればOK。
透かしのデザインは許容範囲ですので、少し遊び心もつのも◎
この懐紙に使われているのは、1300年の歴史を誇る美濃和紙。
山紫水明の地、岐阜県美濃市の自然に育まれ、職人の手によって丁寧に漉かれた和紙は、しなやかで、やさしい肌触りが魅力です。
価格:500円
楊枝(菓子切り)
主菓子を切り分けていただく際に使用する楊枝(菓子切り)も必須アイテムです。素材は竹製の黒文字が伝統的ですが、最近ではステンレス製の菓子切りも人気があります。
お茶会によっては、黒文字の楊枝が添えられている場合もあります。その場合は、添えられた楊枝を使っても構いません。ただし、自分専用の菓子切りを持参することで、茶道への心遣いが表現できます。
ステンレス製の菓子切りは、手入れがしやすく衛生的なのでおすすめです。楊枝は専用の楊枝入れに入れ、さらに懐紙に包んで持参するのがマナーです。
扇子(せんす)
茶道用の扇子は、お茶会において最も重要な持ち物の一つです。実際に仰ぐためのものではなく、挨拶をする際に膝の前に置いて、自分と相手の間に結界を作り、相手への敬意を表すという儀礼的な意味を持つ道具です。
茶道用の扇子は、一般的な扇子とは異なり、骨が少なく薄く、また一回り小さく作られています。男性用は約19.5cm、女性用は約18cmと、懐紙と同様にサイズが異なりますので、購入の際は注意しましょう。色は男性用が白または地味な色、女性用は柔らかな色合いのものが一般的です。
改めて強調しますが、扇子は開いて仰ぐことはありません。閉じたまま使用するのが茶道の作法です。道具拝見の際にも、扇子を膝の前に置いて拝見します。
【流派別】持参すると良いもの
茶道には表千家、裏千家、武者小路千家などの流派があり、流派によって使用する道具が若干異なります。招待されたお茶会がどの流派のものか分かっている場合は、以下のアイテムも用意しておくと良いでしょう。
▪️袱紗(ふくさ)
袱紗はお点前の際に道具を清めるために使う絹の布です。亭主(お点前をする側)の場合は袱紗を帯に挟んで使用しますが、実はお客様として参加する場合でも、袱紗を持参することがあります。
色には決まりがあり、男性は紫色、女性は赤や朱色を使用するのが一般的です。正式な茶事に招かれた際は、袱紗を持参することで、茶道への理解と敬意を示すことができます。
なお、お点前の種類によっては使わない場合もありますので、初めての参加の際は、主催者に確認すると安心です。
▪️古帛紗(こぶくさ)【裏千家】
裏千家の茶会では、「古帛紗」という小さな布を使用することがあります。これは濃茶をいただく際に、お茶碗を乗せるために使うほか、道具を拝見する際にも用いられます。通常の袱紗よりも小さく、華やかな柄が施されていることが特徴です。
古帛紗は色や柄が多種多様で、季節や好みに合わせて選ぶ楽しみがあります。お茶会に何度か参加して慣れてきたら、自分らしい古帛紗を見つけるのも、茶道の楽しみの一つです。
裏千家のお茶会に招かれた際は、古帛紗を用意しておくと、よりスムーズにお茶会を楽しむことができます。
▪️小茶巾(こぢゃきん)【裏千家】
小茶巾は、濃茶をいただいた後にお茶碗の飲み口を清めるために使用する小さな布です。こちらも主に裏千家で使用されます。
小茶巾は湿らせて使うため、防水仕様の「小茶巾入れ」と一緒に持参すると便利です。濡れた小茶巾を懐紙で包むこともできますが、専用の入れ物があると衛生的で安心です。
小茶巾入れは、普段は名刺入れやカード入れとして使っている方もいるほど、日常使いできるサイズと機能性を持っています。茶道の道具は、日常生活にも取り入れやすいのが魅力です。
【便利グッズ】持っていると安心なもの
必須ではありませんが、持っていると快適にお茶会を楽しめる便利なアイテムをご紹介します。
袱紗ばさみ(懐紙入れ)
袱紗ばさみは、袱紗や懐紙、楊枝などをまとめて入れておくための小さな袋です。懐紙入れ、数寄屋袋とも呼ばれます。
バッグの中でこれらの小物が散らばらず、取り出しやすくなるため、大変便利です。特に洋服で参加する場合は、道具を入れたまま席に入ることになるため、袱紗ばさみがあると非常に重宝します。

数寄屋袋(すきやぶくろ)
数寄屋袋は、茶道の小物を入れて持ち運ぶための袋です。袱紗、懐紙、楊枝、扇子などをすべてまとめて入れることができます。
お茶会では、数寄屋袋ごと席に持ち込むこともできますし、コートなどと一緒に風呂敷に包んで預けることもできます。懐に直接懐紙などを入れる場合は、扇子は帯に挟みます。
数寄屋袋があると、持ち物の管理がしやすく、見た目にも美しく整います。
替えの足袋・靴下
お茶室に入る際は、清潔な足元であることが大切なマナーです。特に雨天時や、お茶室まで距離がある場合、足袋や靴下が汚れてしまう可能性があります。
着物で参加する場合は白足袋を、洋服で参加する場合は白または落ち着いた色の新しい靴下を、替えとして持参することをおすすめします。お茶室の前の控室や待合いで履き替えることで、清々しい気持ちでお茶会に臨むことができます。
足袋カバーを使用するのも良い方法です。会場に到着するまで足袋カバーをつけておき、お茶室に入る直前に外すことで、白足袋を清潔に保つことができます。
正座椅子
正座が苦手な方や、長時間の正座が難しい方には、携帯用の正座椅子がおすすめです。正座の姿勢をサポートし、足のしびれを軽減してくれます。
持ち運びしやすいコンパクトな商品を選ぶと良いでしょう。ただし、お茶会によっては正座椅子の使用が難しい場合もありますので、事前に主催者に確認することをおすすめします。
アクセサリーケース
お茶会では、指輪やネックレス、腕時計などのアクセサリーを外すのが絶対的なマナーです。貴重な茶器を傷つけないためです。
小さなアクセサリーケースを持参しておくと、外したアクセサリーを紛失することなく、安全に保管できます。会場に到着してから外すのではなく、自宅を出る前に外しておき、ケースに入れて持参すると、さらに安心です。
風呂敷
コートや荷物を包んで預ける際に、風呂敷があると便利です。脱いだコートや上着を風呂敷に包んでおくと、コンパクトにまとまり、受付でも預けやすくなります。
また、お茶会でいただいたお土産を持ち帰る際にも活躍します。風呂敷は茶道の精神である「和敬清寂」を体現する美しい日本の伝統文化です。お茶会にふさわしいアイテムと言えるでしょう。
お茶会にふさわしい服装と身だしなみ

お茶会では、持ち物だけでなく、服装や身だしなみにも気を配ることが大切です。清潔感があり、茶室の雰囲気に調和する装いを心がけましょう。
基本的な身だしなみのマナー
お茶会に参加する際は、以下の点に注意しましょう。
香りに関するマナー
香水や香りの強い整髪料は控えましょう。お茶会では、お茶やお香の繊細な香りを楽しむため、強い香りは他の参加者の妨げになります。
同様に、匂いの強いハンドクリームも控えるのがベターです。お茶会の前日から、香りの強いボディケア用品の使用は避けることをおすすめします。
メイクに関する注意
派手な化粧は避け、ナチュラルメイクを心がけましょう。特に口紅は、お茶碗に着いてしまうと取れにくいため、控えめにするか、ティッシュで軽く押さえてから参加すると良いでしょう。
アクセサリーは外す
指輪、ネックレス、腕時計、ブレスレット、ピアス、イヤリングなどのアクセサリーは、大切な茶器や茶道具を傷つける恐れがあるため、すべて外しましょう。結婚指輪も含め、お茶会の間は外すのがマナーです。
会場に到着してから外すのではなく、自宅を出る前に外しておくと、紛失の心配がありません。小さなアクセサリーケースに入れて持参すると安心です。
髪型・爪
髪の長い方は、すっきりとまとめ髪にしましょう。お辞儀をした際に髪が顔にかかると、所作が美しく見えませんし、お茶碗に髪が入ってしまう可能性もあります。大きな髪飾りやキラキラした飾りは避け、シンプルなまとめ髪を心がけます。爪
爪は短く整え、ネイルアートは控えめにしましょう。派手なネイルアートや長い爪は、茶道具を扱う際に不向きです。ベージュやピンクなど、自然な色のネイルがおすすめです。
携帯電話
携帯電話は必ずマナーモードに設定するか、電源をオフにしましょう。茶室は静寂を大切にする空間です。できれば、お茶会の間は携帯電話をバッグにしまっておくことをおすすめします。
着物での参加
お茶会に着物で参加する場合、カジュアルすぎない装いを選びましょう。茶道の服装には、いくつかのポイントがあります。
基本のルール
・襟は白が基本です
・足袋は白を着用します
・足袋カバーや替えの足袋を用意しておくと、茶室に入る際に清潔な足元を保てます
・コートや羽織は、茶室に入る前に脱ぎます
男性の着物
お召しや無地の紬に袴を合わせた、茶席の雰囲気に合った落ち着いたコーディネートがおすすめです。全体の色味は、グレー、紺、茶色など、落ち着いたトーンでまとめましょう。
袴は足元が汚れにくく、正座もしやすいためおすすめです。袴を着用する場合は、下にステテコを履いても構いません。袴なしで着物に角帯を締める場合は、必ず長襦袢を着用し、着崩れを防ぐために腰ひもをしっかり結びましょう。
女性の着物
染めの着物に袋帯、または格のある名古屋帯を合わせるのがおすすめです。訪問着、付け下げ、色無地などが適しています。
紬はカジュアルな着物とされているため、一般的なお茶会にはあまり適していません。ただし、無地染めの紬の場合は、格の高い帯を合わせることで問題なく着用できます。
招待された際は、事前にどのようなお茶会か(茶事なのか大寄せなのか、格式はどの程度か)を確認しておくと安心です。お茶会のテーマや季節、雰囲気に合わせたコーディネートを楽しみましょう。
派手すぎる柄や、季節外れの柄は避けましょう。
洋服での参加
「着物を持っていない」「着付けができない」という方でも、洋服でお茶会に参加することは全く問題ありません。露出の少ない、綺麗めな装いを選びましょう。
洋服での基本ルール
・清潔な白い靴下を着用します(必ず替えを持参)
・お茶室の前の控室や待合いで綺麗な靴下に履き替えます
・雨天などで汚れる可能性があるため、新しい靴下を持参するのがおすすめです
・コートやジャケットは、茶室に入る前に脱ぎます
男性の洋服
シャツにジャケット、またはスーツが適しています。ビジネスカジュアルやオフィスカジュアルでも構いませんが、落ち着いた色(紺、グレー、ベージュなど)を選びましょう。
▪️避けるべき服装
・ジーンズ(カジュアルすぎるため)
・Tシャツ、スウェット
・派手な柄のシャツ
・サンダル
ジーンズは見た目の問題だけでなく、生地が固いため正座をすると足が痺れやすくなります。
女性の洋服
スーツ、ワンピース、ブラウスとスカートの組み合わせなど、オフィスカジュアルからセミフォーマルな装いがおすすめです。

こちらネイビーのワンピースです。
襟は、クラシカルな形で色味は日常に合わせてオフホワイトを使用。甘くフォーマルデザインに仕上げ、襟や袖の形状にはほんのりモードなエッセンスをプラスされた、程よい可愛さがあるワンピです。
スカート丈のポイント
・膝丈またはミディ丈(膝下丈)が適切です
・お茶会では立ったり座ったりする動作が多いため、動きやすい丈を選びましょう
・くるぶし丈のマキシスカートは、裾を踏んでしまう可能性があるため避けた方が無難です
素材と色
アクセサリーを外す必要がありますが、光沢のある素材(サテン、シルクなど)やレースがあしらわれた服を選べば、華やかな印象になります。色は、白、ベージュ、パステルカラー、グレー、紺など、上品で落ち着いた色がおすすめです。
パンツスタイル
パンツスタイルでも参加できますが、ジーンズは避けましょう。テーパードパンツやワイドパンツなど、きれいめのパンツに、ブラウスやジャケットを合わせると良いでしょう。
お茶会の流れと基本マナー

お茶会がどのような流れで進むのかを事前に知っておくと、当日も落ち着いて参加できます。ここでは、一般的なお茶会の流れと基本的なマナーをご紹介します。詳しい茶道の作法については、別の記事でも解説しています。
1. 受付・待合い
会場に到着したら、まず受付を済ませます。コートや上着、大きな荷物は、この時点で預けます。風呂敷に包んでおくと、預ける際もスマートです。
待合いでは、他の参加者の方と静かに待ちます。この時、靴下を清潔なものに履き替えておきましょう。
2. 席入り・挨拶
茶室への席入りが始まったら、順番に入室します。茶室に入る際は、敷居を踏まないように注意しましょう。
席に着く際、初めての参加者は、「正客(しょうきゃく)」や「末客(まっきゃく/お詰)」など、問答や配慮が必要な席を避けた方が無難です。特に正客は、お道具やしつらえについて亭主と問答する代表の役割があるため、茶道の経験が浅い方には負担が大きいでしょう。「二客」や「三客」など、中ほどの席が良いでしょう。
席に着いたら、まず亭主(主催者)が挨拶を行います。通常は正客に最初に挨拶し、その後、他の参加者にも挨拶をします。挨拶には適宜礼を返しましょう。
この時、扇子を膝の前に置いて、敬意を表します。
3. 床の間の拝見
お茶会では、床の間に掛けられた掛け軸やお花を拝見することも、大切な楽しみの一つです。正客から順に拝見し、季節や茶会のテーマを感じ取りましょう。
4. お点前の礼
お点前が始まる時や終わる時など、お点前さんが礼をするのに合わせて、参加者も礼をします。いつ礼をするのか分からない場合は、周りの方の動きを見ながら行動すると良いでしょう。
5. お菓子をいただく
お菓子が運ばれてきたら、以下の手順でいただきます。
1. 左隣の人に「お先に」と声をかけます
2. 菓子器を両手で持ち上げてから正面に置き、軽くお辞儀をします
3. 懐紙を膝の前に広げます
4. 菓子器からお菓子を懐紙に取ります
5. 楊枝(菓子切り)でお菓子を一口大に切り分けていただきます
6. 菓子器を次の人に渡します
お菓子は、お茶をいただく前に全部食べ終えるのがマナーです。ただし、食べきれない場合は、無理をせず懐紙に包んで持ち帰っても構いません。
6. お茶をいただく
お茶は、以下の手順でいただきます。
1. お運びさんからお茶碗を受け取ります
2. 左隣の人に「お先に」と声をかけます
3. お茶碗を右手で取り、左手に乗せます
4. 「お点前頂戴いたします」と唱えながら、軽く一礼します
5. お茶碗を時計回りに2回(約180度)回し、正面を避けます
6. お茶をいただきます
7. 飲み口を指のヘラで軽く拭きます
8. お茶碗を反時計回りに2回回し、正面を戻します
9.お茶碗を拝見します
10. お茶碗をお運びさんに返します、または自分の前に置きます
▪️お茶碗を回す理由
お茶碗の「正面」(最も美しい絵柄がある側)は、亭主が客に向けて出してくれます。その正面に直接口をつけるのは失礼にあたるため、時計回りに回して正面を避けてからいただきます。
▪️最後の一口「水切り」
最後の一口を飲む際に「ズズッ」と音を立てることを「水切り」と言います。これは「美味しかったです、ありがとうございました」という感謝の気持ちを表す作法です。遠慮せず、しっかりと音を立てましょう。
お茶碗の柄や形を鑑賞することも、お茶会の楽しみの一つです。
7. 道具の拝見
お点前が終わると、茶碗や茶入れ、茶杓などの道具を拝見する時間があります。これは正客から順に行われます。
▪️拝見の作法
・道具を拝見する際は、まず扇子を膝の前に置きます
・道具を手に取る際は、両手で丁寧に扱います
・腕を桃(太もも)にしっかり固定し、低い位置で拝見します(落として割れる可能性を低くするため)
・指輪などのアクセサリーが茶碗に当たらないよう注意します(だからこそアクセサリーは外す必要があるのです)
・茶碗の裏側の高台(こうだい)や、作家の銘など、細部まで鑑賞しましょう
拝見が終わったら、次の方に丁寧に渡します。
8. 終わりの挨拶・退席
最後に亭主と挨拶を交わして、お茶会は終了です。挨拶の後、床の間や点前座の道具を再度拝見したり、各自で退席します。
退席する際も、敷居を踏まないように注意し、茶室を出る前に一礼することを忘れずに。